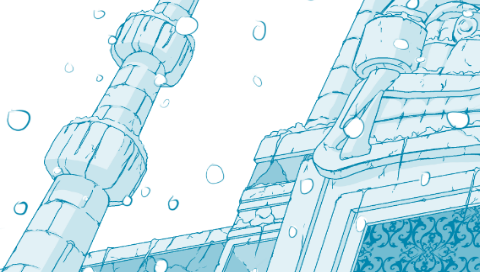
緞帳役者は、かく語りき。
「何だ、アイツら来ねぇのか」
ふてぶてしそうな声が室内に響く。
声の主は、今月も来客が無い事を察すると、近くに置いてある酒樽に手を伸ばした。
普通の人間なら運ぶのに数人掛かりそうな重さのそれを軽々と片手で持ち上げ、まるで茶でも飲むように煽る。
汚らしく口の端から酒を垂らしてみせると、もう一方の腕でクイッと拭いた。
「やっと暇を潰せる相手が来たかと思ったが、怖じ気づきでもしたのか?」
「さぁ、ボクに知る由もないよ」
「何だよつれないな。フラフラ外に抜け出してはあの一族を付け回しているから、事情の一つも知ってるだろうに」
「残念ながら。ボクだってようやくココから解放されるものだと思っていたのに、拍子抜けサ」
心底呆れたような態度で目の前に居る少年は答えている。
その様子を見た声の主は、不気味な笑みを浮かべて見せた。
「解放される、かぁ。いいねぇ。俺もここから出て行きたいもんだゼ」
出られるもんなら、な。と言い、声の主は自らの手に埋め込まれた玉を一目した。
そして、そのまま二杯目の酒樽に手を伸ばす。
「あいつらも酷ぇよなぁ。勝手に作り出して、都合が悪いから無かったことにして、すっかり忘れた頃に再利用しやがる。命を何だと思ってるんだか」
「捨てたオモチャに愛着があるとでも? 思い出して貰っただけでも感謝しろって位は考えてるかもネ」
「ケッ、つくづく性格が悪いヤツらだ。よくもまぁ、いけしゃあしゃあと善人ぶれるもんだよ」
二本目の酒樽が空くと、それはグシャリと握り潰された。
「そうじゃなきゃ、こんな大掛かりで回りくどい、悪趣味な余興なんて思い付く筈ないだろ?」
少年は、そう言うと透けた体を固く閉じられた扉の方へと向ける。
外は嵐のように吹雪いていると言うのに、扉一枚阻まれたこの場所では物音の一つもしない。
まるで別世界にいるかのように、ただ二人の会話が響くのみだ。
「復讐を遂げる日まで、安らかに眠るなかれ、か」
「外に置いてあるデカブツの事か。それがどうしたよ」
「その日までにどれだけの命が粗末に扱われるのかな、ってね」
声の主が三杯目の酒に手を伸ばすのを見ながら、少年が妖しく笑みを零し問いかけた。
「ねぇ、たかが8ヶ月の父親が4ヶ月の娘を連れて敵討ちだなんて、あの人達も大概無茶してると思わないかい?」
「……わざわざ乳飲み子を使ってやる所業じゃあねぇよなぁ」
「さすがにあの人達でも簡単には事を運べなくて、色々と問題を抱えているみたいだけどサ」
少年はどこからともなく出した杯を、まだ持ち主が口を付ける前の酒樽に突っ込み、酒を掠める。
「やるだけやっておいて、最終的にゃ俺達に全部おっ被せるつもりなんだから、こっちもいい迷惑だゼ」
「いいじゃないか、向こうがその気ならボク達だって堂々と利用してやればいいんだし」
杯に口を付け掠め取った酒を飲み干すと、少年は不機嫌な表情をした。
「うわ不味っ。よくこんなの飲んでいられるね」
「仕方ねぇだろ。この辺じゃまともな酒が造れる所なんてありゃしねぇ」
それもこれも全部俺達の所為なんだろ? と、声の主は三杯目の酒に口を付けながら言う。
「あの一族も、あいつらに好き放題されて可哀想なこった」
少年が物珍しそうな顔で声の主を見た。
「あれれ、同情してるの?意外だなぁ」
「同病相憐れむ、って奴さ。だからって言って手心を加えてやるつもりはねぇけどな」
「へぇ、そんな難しい言葉知ってたんだ」
「馬鹿にすんなよ。これでもお前さんより長く生きてるんだ」
飲み終わった樽をその辺に投げ捨てると、酒の在庫が切れたことを確認して、声の主はその場でゴロンと寝転がった。
「さぁて、俺はもう寝るゼ。今年はやる事が無くなっちまったしな」
「ま、ゆっくり休んでなよ。その間のことは次に起きたときにでも話してあげるさ」
「おう、少しは楽しい状況になってるといいんだがなぁ……」
そう言うと、声の主はすぐに大きないびきをかき始める。
眠り始めたそれを一目すると、少年は少しだけ微笑み、もう聞こえていないだろう相手に声を掛けた。
「……それじゃあ、また来年」
タイトル通りの、悪党共の饗宴。
「饗宴」は「共演」と掛けてます。
ゲーム内では見られなかった二人の会話ですね。
全体的にぼやっとした内容なので語り辛いのですが、取り敢えずこの二人はそれなりに関係性は良さそうです。
仲良しこよしでは無いし、裏切るときは裏切るし、互いがどうなろうと知ったこっちゃない。
そう思ってはいるけど、今のところは運命共同体。ひとまずは協力し合っておきましょ。
どうせお互いやれること限られてるし。
……そんな感じです。
実情はどうあれ、今のところは仲間なので、ね。


